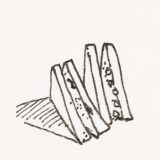細かい雨が降る2月の土曜日、午後1時。
7才の息子は、バスケットボール体験教室に参加した。
彼は週末になるといつも、家でぼくと1on1をして遊んでいるので、バスケットボールに興味を持ち始めているのだ。
でも、大きいボールを使い、正しいルールで大人が教えるバスケットボールは今回が初めて。天井の高い体育館に入り、経験のある2,3年生たちを見て、彼の表情は固くなった。
20人ほどの2,3年生の子どもたち。 先生は、B-LEAGUE京都ハンナリーズの運営も担当されている20代の男性。 厳しさではなく動きの意図、難しさではなく動きの興味深さを伝えている。
息子は、初めての場所、初めて会う先生、初めて会う子どもたちの中に入っていく。
ボールハンドリングから体験教室は始まる。 息子は困りながら、先に進む少年少女たちの動きを観察し、見よう見まねでボールと体の関係性を学んでいく。
重心移動と足の連携、床に反射するボールの軌道、右手と左手の可動域の違い、重いボール、体とボールの速さの違い。 これまで一度もやったことのない規則の連なり。
開始5分後、1回だけ彼は不安そうにぼくの顔を見て「できひん」と言うように首を横に振る。 でもそれだけすると、ボールハンドリングのトレーニングに戻った。
ドリブルの組み合わせは次第に複雑になる。
15分ごとの休憩で息子は水を飲み
「つかれた」
と言い
「あとどれくらいで終わるん?」
と聞く。
ぼくは
「2時20分まで。あと40分くらいやな」
と答える。
彼は、その時間が自分にとって長いのか短いのかまでは分からなかったように見えた。
トレーニングは30分、40分と続く。
応用は、ドリブルからのレイアップシュート、コートの端から端まで走ってからのレイアップシュートに移行する。 もちろん、息子はレイアップシュートを知らない。 彼の得意技、千葉ジェッツの富樫勇樹選手を真似した「富樫シュート」は、家の小さなゴムボールでしかできないのだ。
息子のシュートは全て空を切る。
重いボールはリングにすらぶつからない。
トレーニングが1時間を過ぎると、3分ゲームが始まる。 7対7のチーム制。息子はAチームになる。経験者は両チームに2名ほど。彼らを中心にゲームは動く。 かといってよく見ると、息子以外の少年少女も特別上手なわけではない。
試合は、14人の子どもたちがボールに群がりながら進んでいく。
ポジションも戦術もない。2,3年生の経験者がドリブルし、シュートを決める。
Aチーム 4 – Bチーム 6
Aチーム 2 -Bチーム 4
Aチーム 0 – Bチーム 2
というスコア。 3分ゲームはさらに続く。
観覧する大人たちは、我が子が走る姿をじっと見つめている。 まるで自身の何かを仮託するように。
息子は、チームというコンセプト、思うようにならないボールの原理、初めて体験する規則の連なりを正面から引き受けている。 心に生まれる恐怖を誤魔化さず、受け止め、立ち向かっている。
息子は走り続ける。
彼は勇気を持った人なのだ、とぼくは理解する。
1度だけ、彼は、ボールをスティールできる瞬間を見つける。それは、 3年生が反対のコートに向かってドリブルを行い、味方の少年にパスをするほんの瞬間。 息子の右手は、確実にパスボールの動線に触れる意図を持っている。 ぼくにはそれが分かる。
でも、あと30センチ足りない。
少年はそのままパスを受け、ゴールに向かい、レイアップシュートを決める。試合終了。
Aチーム 4 – Bチーム 4
Aチーム 2 – Bチーム 6
という結果。
彼は1度もボールにさわれなかった。 自分のチームが勝ったのか負けたのかさえ分かっていないし、もう興味も失っている。
そのようにして、バスケットボール体験教室が終わる。
彼はすぐに体育館を後にする。 緊張と疲労に包まれ、悔しさと恥ずかしさを感じながら。プライドはくじかれた。
外に出ると、雨は止んでいる。
2人は無言で家に帰る。
1週間たった今も、ぼくは考え続けている。
ドリブルの音が響く天井の高い体育館で走り続ける息子から、無償で受け取った何かについて。