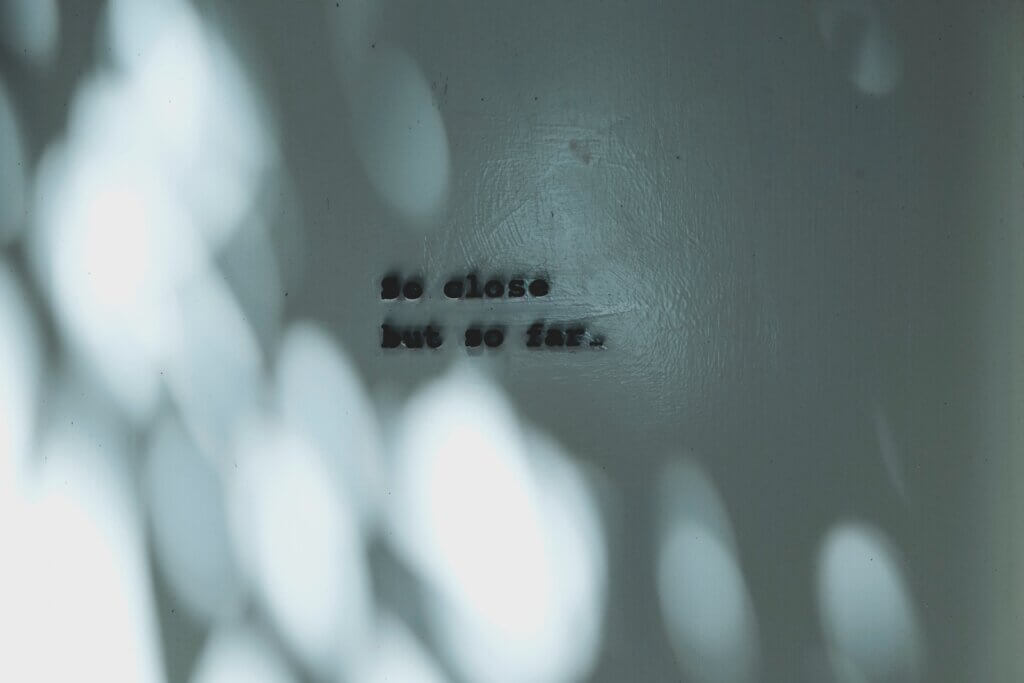
2008年、夏。
小さなお好み焼き屋のテーブル席。
知り合って数か月の3人の同僚。
そのなかの一人、洋裁教室の先生がこう言いました。
「大学では落研にいました……」
そして、顔を真っ赤にしました。
ぼくともう一人の同僚は、目を見合わせ笑いました。
どうしてかというと、その女性は職場では落ち着いていて、誰とでも一定の距離を保つ、厳しい先生だったから。
その先生が、のちにぼくと結婚し、2人の子どもを生んでくれる人だとは知らずに。
当時28才のぼくは、「人生で結婚することはない」と割り切っていました。
なぜそう考えていたのか?
それは、ぼくの人生が、まるで終わらないジェットコースターに乗っているようなものだったから。
誰かとそれを共有したいとも、できるとも思っていなかったから。
暴力に満ちた家庭で、ぼくは育ちました。
生まれる前から
「勉強でも運動でも、絶対一番になれ」
「絶対会社を継げ」
と命令され続けてきました。
タバコとアルコールと暴力が常備された台所で。
泣いている母と姉と兄を見ながら。
6才から摂食障害になり、小学4年~5年生の時に1年間休学します。
そのあとも、卒業まで不登校の繰り返し。
教育機関ではずっと、班長、生徒会長、運動部の部長などの組織長に推薦され続けました。
それは、自分が優れているからではなく、教師の側からも生徒の側からも、要求しやすい態度を身につけていたから。
要求されるすべての役職で「自分の能力以上を出して燃え尽きる」というサイクルを繰り返しました。
それは、求めに応えられなくなった時点で、死が待っていると感じていたから。
文字通り必死になり、期待以上のものを提示し続ける少年。
中学校は3年の3学期をほとんど休み、高校は7日で退学しました。
高校生活8日目。
限界に至っていることを自覚します。
言語障害になり、映像を思い描くことができなり、記憶を想起することもできなくなっていました。
数ヶ月後、他県にある全寮制の農業高校に入ることを決めます。
動機は、両親の会社を継ぐために農業を勉強しなければいけない、というもの。
受験に合格すると、3年間の寮生活を始めます。
でも、高校3年生のとき、ぼくは言います。
会社を継ぎたくない、自分として生きていきたい、と。
母は深く泣き、父は激しく怒りました。
そのような経緯のまま、とある大学のスペイン文学科に入学。
必要最低限の出席日数を出席。それ以外は授業を休み、古いアパートの一室で1日10時間以上、7か国語の独学に没頭しました。
「どんなにもがいても、結局、両親の会社を継がなくてはならないのだろう」という観念と闘いながら。
大学3年生の夏。
両親の会社に、コンサルティング会社の社長(とても太った50代の男)が現れます。
彼は、手際よく、ぼくとぼくの母の心を掴むと、数千万円のコンサル費用を手に入れ、姿を消します。
地域で有名な詐欺師でした。
その数か月のあいだに、姉が結婚。
姉の夫が婿養子として会社を継いでいました。
22年間、全てを捧げてきたテーマが、一瞬で姿を消しました。
生き続ける唯一の根拠だった正義感とともに。
残ったものは、言語障害・思考不全、失われた記憶、失われた想像力、深い疲弊。
世界に提供できるものは、だいぶ前に全て出し尽くしている。
何もないところから何かを生み出すのは、もう無理だ。
世界はこれ以上、何を、何のために搾取するのか?
自分が空洞であることを認めること、それがどのような空洞かを理解すること。
それ以外に、やるべきことはないように思えました。
知人が言います。
「お前は、死んでるみたいに生きてるよな」
確かに。それは認める。
認めるし、そんなことはずっと前から君より深く知っている。
知った上で生き延びることを選択し、今日も一日生き延びているのだから。
君は想像できるだろうか。
抗えない外圧によって、生まれたときから家族と自分は死に向かう工程に組み込まれている。
いくら努力しても何も変更できず、むしろ状況は悪化していく。
その状況を正確に理解しながら、耐え続けることを。
それが、具体的にどういう日々で、どんなディテールなのか。
生き延びるためには、どんな判断力が必要とされるのか。
生き延びながら、何を捨てなければならないか。
生き延びながら、何を夢想する余地があるのか(ないのか)。
2004年、春。
大学を卒業したぼくは、1年間アルバイトを行い、アルゼンチンに向かいます。
アルゼンチンのコルドバに2年半滞在。そこでスペイン語、英語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語の基礎を学びました。
2007年、夏。
帰国。
2008年、春。
洋裁教室兼オーガニックカフェで働いていたとき、洋裁教室の先生に出会います。
2008年、冬。
午後11時。五条河原町の交差点。
ぼくは、洋裁教室の先生に言います。
「好きです。付き合ってください」
2009年、冬の終わり。
先生から「よろしくお願いします」という答えがかえってきます。
そのようにして、付き合いが始まりました。
(10年以上たった今も、ぼくたちは敬語で話します)
でも、ジェットコースターから降りていないことを、ぼくは知りませんでした。
その3年後、ぼくは過労でヘルニアになり、飲食業界から身を引きます。
おなじ時期、第一子が誕生。
洋裁教室の先生は、じっと耐えていました。
結婚したばかりの夫がヘルニアになり、同時に職を失い、生んだばかりの子どもが泣く家で。
飲食業界から別の業界を選ばざるを得なくなり、何度も職を変えます。
移動する組織ごとに、自分のスキルセットをゼロから組み立てなおし、適応させ続ける。
タフな時間のはじまり。
アルゼンチンから帰国した2007年から2018年までの11年間(27才から38才の間)、所属した組織は9つ。
1. 新築マンションのリペア会社
2. 芸術家の助手
3. 洋裁教室兼オーガニックカフェ
4. 創作イタリアンカフェ
5. ホテル内レストラン
6. 生鮮食品会社
7. アクセサリー製造販売会社
8. Webサイト制作会社
9. バックオフィス企業のWeb事業部(2017年の夏~)
おそらく、今もぼくは一人で、同じアトラクションに乗っているのでしょう。
いずれにせよ最初から、いつ乗ったのかも知らないし、降り方もわからなかったのです。
そもそも人は、自分がどのような条件のアトラクションに乗っているのか、どこまで知ることができるのでしょう?
妻は、その間ずっと、ぼくに対して一定の距離を保ち、見守り、支えてくれました。
その姿勢に、どれほど救われてきたか。
安易に手を差し伸べるわけでもなく、「わかるよ」と理解を示すわけでもない。
結果に対して「いいですね」とも「よくない」とも判断しない。
ぼくという人間がどんな人なのかをずっと見ている。
淡々としたまなざし。
そのようなやり方で評価する(評価しない)人が隣に居なければ、ここまでやってこれなかった。
そして、自分の人生を定義できなかった。
ときに、思いを言葉にすることは、驚くほど簡単です。
同時に、それを言ったらウソになるから言えないことが世の中にはたくさんある。
そう、感じてきました。
でも、今はもうそのときではありません。
だからぼくは彼女にこう言います。
「一緒にいてくれて、ありがとう」

