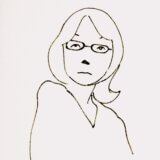1990年8月
1990年8月。
数年前から過食が習慣化していた10才のぼくは、2学期から小学校に行くことをやめます。
1年間不登校生活を行い、卒業するまで、出席と欠席を繰り返しました。
1995年4月
1995年4月。
高校に入学します。
2週間目の月曜日、高校に行くことをやめました。
15才の新しい生活の1日目に起こったこと
その日の朝、不思議な景色が広がっていました。
家の一階では、両親が激しく喧嘩をしていて、僕はそれを喜ばしく思っているのです。
そして、頭の中には2人の思考する人物がいて、それぞれ自律的に思考を重ねています。
1人目は頭の上の方にいました。
思考速度は速く、論理的で、正義感に溢れ、批判的な人でした。
彼は、暴力性に直接結びついているようでした。
2人目は、頭の下の方にいました。
ゆっくり考え、ゆっくり判断しようとしていました。
まるで、言葉という概念を知ったばかりの2才の子どものように。
3人目のぼくは、2人のあいだで放心しています。
頭が熱い。
1階では、両親が口論を続けています。
別の場所で、感情的にこの状況を喜んでいる自分がいる。
どれがぼくだ?
複数人の自分が、同時に、離れた場所にいました。
自分がどの自分か見分けがつかなくなることを恐れながら、ぼくは3人目の自分を自分とし、そこに根を据えました。
見知らぬ場所へ、自分たちがそれぞれ拡散しないうちに。
(3人目の自分を選んだことが正しかったのか、3人目の自分を選んだ自分は誰なのか。それはわかりません。とにかくそのときは、あまり残されていない時間の中で、確からしい自分を選び、しがみつき離れないことが必要だった、としか言えません。)
以降、言語障害を抱え、思考と感情が分離し、記憶想起の能力が消えていきます。
圧倒的な自己乖離。
それが、15才の新しい生活の1日目に起こったこと。
気がつくと、頭の中で映像を想像することができなくなっていました。
テレビや映画を見ると、頭が痛い。
視覚情報が、気分を悪くする。
情報に意味づけができないので、情報間に関連を付けられないまま、視覚情報が増え続ける。
意味が付与されない情報が飽和し、頭が熱くなり、苦痛に変わる。
結果、2つの瞼を閉じる。
閉じたところで、何も変わらない。
そして、記憶と感情の機能が低下する。
当然それらの症状は、生きることを難しくしました。
自尊心に対して最も致命的だったあり方
自尊心に対して最も致命的だったあり方は、物事の判断基準を「客観的な正しさ」と仮定していたことでした。
視覚的想像力・記憶・感情が分離する前から、正しさを神の視点に配置していたことは、とてもよくない組み合わせとして機能し、ぼくのその後の人格体験に、大きな影響を及ぼしました。
結果、どうなったか?
長期的に不愉快な関係性を生みました。
具体的には「困難をともに乗り越え、関係性を培った人々」と、壊滅的な別れ方をするようになります。
そしてそれを繰り返す。
なぜなら、ともに苦難を乗り越えたあと、自分が正しいと信じている本人が、全く救われていないことに気がつくから。苦難のあとの状況を批判し始めるから。たとえ、自分が間違っている、客観的な正しさなどどこにもない、とどこかで感じていても。
■それまでの判断基準
・客観的な正しさがあると信じる
・神の視点を配置(一人称からの離脱。神を仮定しないまま三人称を置く。そこには「救い」への意志-仕組み-概念がない)
■言語障害の症状
・3つの乖離
1. 視覚的想像力と自己の乖離
2. 記憶と自己の乖離
3. 感情と自己の乖離
・記憶想起能力の低下
■結果
・言葉の用途の傾向:外部批判と自己擁護の方向性へ
→ルサンチマン的な言語の用法
→自尊心を破壊する仕組みを所有することに
2005年
アルゼンチンのポルトガル語学校で、ブラジル人の先生に愛について質問する
2005年。
アルゼンチンに住み、ポルトガル語の学校に通っていたときのある授業での出来事。
ぼくは、ブラジルの女性の先生に聞きます。
「愛」という言葉の意味がわからない。
なぜなら「愛」という言葉は外国からやってきたものだから。
すると、彼女は口を閉じます。
笑顔のまま。
悲しそうに。
2つ隣の席に座る60代の白髪の男性が言いました。
「愛」なんてただの言葉だよ。
それは自然に感じるもの。
アルゼンチンでも、ブラジルでも、日本でも。
それは変わらないよ。
今も昔も。
ブラジルの先生は、そっとうなずき、何も言いません。
あまりにも未成熟な日本人青年を、傷つけずに送り出すように。
ぼくは、アルゼンチンのポルトガル語教室よりも離れた、誰も知らない場所に、一人でいることを確認しました。愛のカタチを知るために来た場所で、自分が、愛から離れた場所にいることを把握しました。そこから愛までの距離がどれくらいあるのか、どの方向にあるのか。それは、ポルトガル語教室のどの教材にも見当たらず、違う場所へ行く必要があるようでした。
2010-2016年
教科書のような文章を書く人
2010年。
喫茶店で働いているとき、先輩のSさんが言いました。
「島津さんは、歩く教科書みたいですね」
2016年。
Webデザイン会社で働いているとき、グラフィックデザイナーのFさんが言いました。
「島津さんは教科書みたいな文章を書きますね」
それらには、心当たりがありました。
15才の乖離した新しい1日から、ぼくは言葉を「自分に対して、世の中の成り立ちを説明するため」に使ってきました。
言語をほぼ持たない彼に対して、テクニカルに世界の成り立ちを説明する方法
15才のぼくは、「頭の上の方の人」と対話を重ねることを諦めました。なぜなら彼は、恨みを原動力として、事象に対して反射的(re-action)に思考する人物だったから。
そうではなく、「頭の下の方の人」に対して説明を行い、日々を生きてきました。彼は言語をほぼ持たない人物でした。ですが、信頼するに足る人物でした。少なくとも、そのように感じさせる倫理性を、ぼくは彼に感じました。物事を理解する速度はとても遅いにもかかわらず(あるいは、遅いからこそ)。
以来、言語をほぼ持たない彼に対して、言語でテクニカルに世界の成り立ちを説明する方法を構築してきました。自分が使うことができる数少ない日本語を選び、意味をひとひとつ再定義し、意味が分かる言葉のみでセンテンスを作りました。そして、彼に語り続けました。まるで外国語を学ぶ人のように(それは実際、外国語だったのだと今では思います)。
最も大切な運用原則:わからないことは、わかるまで、わからないとする
例えば、ぼくはまず、「わからないことは、わかるまで、わからないとする」ことを最も大切な運用原則としました。自分のペースで、自分のために言葉を構築すること。それを実践しなければ、全く意味がないからです。ひとつの言葉を定義するのに数年かかることも普通です。
意味=広さ・価値=高さ
その上で
・意味=広さ(空間における横の広がり)
・価値=高さ(空間における縦の広がり)
と定義しました。
数=動詞的仮説・時間=数を使用した仮説的枠組み
そして
・数=仮説(「分断する」という意味の動詞としての)
・時間=「数(動詞的仮説)」を使用した、現実世界に部分的に有効に効果を発揮する仮説的枠組み
と定義しました。
世界を構成するファンダメンタルな項目は何か?を考え、項目群を組み合わせ、世界が構築できるかを測り続けるのです。そこから、自分が定義した言葉を増やしていき、自分のための思考の枠組みを作っていきました。
そのほかの仮説
・記憶は、生まれた家の形を原型としている
・視覚は、視覚的情報を反射的に見せるが、それは、視覚的仮説である
・思考と肉体の中心には呼吸がある
・1,2,3まではわかる。だが、4以降はわからない
・0とは数字でなはない
・言葉は付置関連である(右に対する左。朝に対する夜。死に対する性)
というように。
見知らぬ高名な学者の思考を借りるのではなく(むしろそこでは、その学者が〇〇という言葉をどう定義しているか?それはなぜか?を精査し、なるほど、と思い至ったのち、そこから立ち去る、ということを行います)、自分の言葉で考えて、自分のためだけの定規を作り、仮説としての世界を構築していく。
書くことで、入り組んでいる構造を具体的に理解し、自律的に駆動させる
言語的なハンディキャプを抱えつつ、社会に出て、日本語でコミュニケーションを機能させ、価値を提供し、対価をいただくためには、「全ての瞬間で、言語をほぼ持たない彼に対して説明する」必要がありました。
それを止めた途端、ぼくの意志と想いは、言葉のカタチを取れないまま死産していきます。
特殊に形成した言語体系を、独自の用法で、メンテナンスし続ける日々。それを行なって、やっと日常に支障なく生きることができる。たとえ話でもなんでもなく、本当にそうして生きてきました。
だから、分からないことは本当にわかりません。誰がどんなにうまく説明してくれても、ダメです。自分の言葉を使って「言語をほぼ持たない彼」に対して説明をしないと、理解に届かないのです。
入り組んでいる。
その入り組んでいる自分の構造を、ひとつひとつ具体的に理解し、自律的に駆動させる方法が「書くこと」でした。
他者とコミュニケーションをとることは、ここまでのプロセスには含まれていません。それは高度すぎるし、もっと時間が必要でした。だから、ぼくの文章のターゲットは常に自分でした。そこに他者は含まれていません。その特殊な言語体系を、他者が理解できる形式に変換することは、まったく別の作業です。そう感じて、生きてきました。
2018年6月
言葉を失った生き残りとしての達成
2018年6月。
自分以外の方々へ向けて、ある文章を書きます。
それはぼくにとって、大きな達成でした。
読者の数や反応の内容ではなく、多くの読者がいる場所へ自分が参加できるようになった、という内的な回復が。言葉を失った生き残りとして、自分を誤魔化すことなく、社会に参加できたことが。自分のためだけに使ってきた言葉を、社会的に機能する言葉に変換するところまで、たどり着いたのだと。
愛がわからないときも、愛を感じるようになったときも、自分で定義した言葉を通して、世界を仮説として構築し、現実と照合することで、日々を生き残ってきました。
15才のときに現れた複数の人々は、ほとんど発話しなくなりました。
でも、今もどこかにいると感じます。
彼らに愛を込めて。